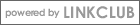February 01, 2006
アメリカン・ドリーム
フィラデルフィアの下町に古くからあるその仕事場に、さえない中年男のポーリーは半分住み込むような格好で居着いていた。郊外の安アパートに一応の部屋があるのだが、家賃を滞納している上、電気も止められてしまっており、帰っても気分が落ち込むばかりなので、自然と職場が住まいのようになってしまったのだ。
しかし、ポーリーが帰れない本当の理由は「酒」だった。
仕事着のポケットにはウイスキーの小瓶がつねに入っており、作業中にちびりちびりとやるのである。
真夏でもはく息が白くなる冷蔵庫の中で行われる作業には、身体を暖めるウイスキーが欠かせない。
一日の仕事が終わる頃にはもう小瓶の酒は空で、当然夜の長さに耐えられないポーリーは、本格的に飲み始める。
そしてアパートに帰れなくなる時間まで酒場に居続け、結果仕事場に泊まることになるのだった。
そんな暮らしが3年半続いている。
12月のある日、本社からやってきたという冷たい目付きの中年男が事務所に居着いてしまった。
無口だが無言の圧力をもった目で人を指図し、仕事場の空気は一気に氷点下まで下がったようだった。
だが、仕事さえしていればその男はうるさいことは言わず、昼間はずっと事務所に閉じこもり、夜遅くになると決まってどこかへ出て行き、明け方ひっそりと帰ってくるのだった。
そんな様子を居心地の悪くなった作業場の詰め所の片隅で、息を凝らしてポーリーは伺っていた。
仕事仲間はその冷徹な男を、恐れを持って「レクター博士」と呼んだ。
朝6時前、「レクター博士」が短い睡眠に入る頃、酒場で知り合ったロッキーが仕事場を訊ねてくる。
以前些細なことでゴロツキにからまれた時に、その場に居合わせたロッキーが助けてくれたのだ。
彼はポーリーにからんだ連中とさして変わらないような生業だったが、いつか成功してこの街を出てゆくという夢を持っていた。
目下のところ彼の成功への近道はボクシングだ。
ロッキーはそのトレーニングの1つとして、ポーリーの仕事場「牛肉処理場」を選んだのだった。
ポーリーの正規の仕事が始まる前に、ほんの小1時間、レーンに吊られて6秒ごとに目の前に流れてくる牛の肉を彼に叩かせることで、1瓶のウイスキーにありつける。
生の肉を殴ることでロッキーは訓練になり、肉は適度に締まって一石二鳥だと彼は思う。
一頻り汗をかいたロッキーはのんびりとこう言った。
「ポーリー、この肉は日本に行くんだってな。フン、ジャップの奴らこのオレが叩いた肉を食って、さぞ喜ぶだろうぜ」
「そうだなロッキー。あいつらはゴミみたいなクズ肉でもありがたがる連中だからな。未来のチャンピオンが叩いた肉なら高値で売れるだろうぜ」
やがて社員がパラパラとやって来た。
いつもお高くとまっている事務員のリプリーの尻を、事務所の階段ですれ違い様に触ってやったら、思い切り横っ面を張られた。
「本気で叩くこたぁないだろうが、親愛の情ってやつだよ・・・」
「ふざけないでポーリー、あんたの汚い手に触られるくらいなら、醜いエイリアンとキスした方がましよ」
“おまえはエイリアンクイーンか”というセリフを飲み込んだポーリーは、こそこそと退散する。
仲間内ではリプリーと「レクター博士」ができているという噂が立っている。
実に不気味なカッブルだ。
階段を下りたところで肩をどやされ、ポーリーは振り返った。
新人のアナキンがニヤニヤして立っていた。
「あんたがエイリアン並みの知能だってこと、彼女まだわかってないんだね」
「うるせー、このカタナ小僧が」
まったく小生意気なガキだ。
なまじナイフさばきに長けているからと、いい気になっている。
手際よく牛肉を捌いていく作業を担当するアナキンの給料は、ポーリーよりずっと上なのも癪に触る。
不愉快な一日の始まりだ。
今日は政府の役人に連れられて日本からの視察団がくるので、絶対に粗相のないようにと「レクター博士」からクギをさされてきたばかりなのだった。
まったく面倒だ。
BSEとかプリオンとかが怖けりゃ牛肉を食わなきゃいいだろう。
政府のバルバティーンとかいうお偉いさんが以前調査に来た時に、いつものように作業員のジェイソンが牛の頭からチェーンソーで真っ二つに割ったら、飛び散った脊髄のかけらがその役人のはげ頭に当たったのだ。
血相を変えた役人がジェイソンを首にしろと怒鳴るし、ポーリーもこっぴどく叱られた。
脊髄を除去しろなんて面倒くさいことを誰が決めたんだ。
きっとアメリカの牛肉に嫉妬したジャップの奴らの嫌がらせに違いない。
金で何でもできるという思い上がったイエローモンキーは、俺たちの生活にまで踏み込んできやがる。
日本が世界のどの辺りにあるかも知らないポーリーだが、つくづく日本人が嫌いになった。
だから、夜中に工場中の牛に怪し気な液体を注射して回る「レクター博士」の行動を盗み見ても、ポーリーは、どうせ日本へ行く牛肉だからと放っておいた。
「レクター博士」のデスクの上に、分厚い「変異型クロイツフェルトヤコブ病」というタイトルの本が置いてあったのを見ても、ポーリーには何のことだかさっぱりわからない。
とにかく今日の仕事をさっさと片付けて、酒を飲んで寝てしまいたかった。
せめて夢でもいいから、行ったこともないティファニーの前で、ヘップバーンのような女から声をかけられたかった。
それがポーリーの唯一のアメリカン・ドリームだったから。
17:46:43 |
mogmas |
|
TrackBacks